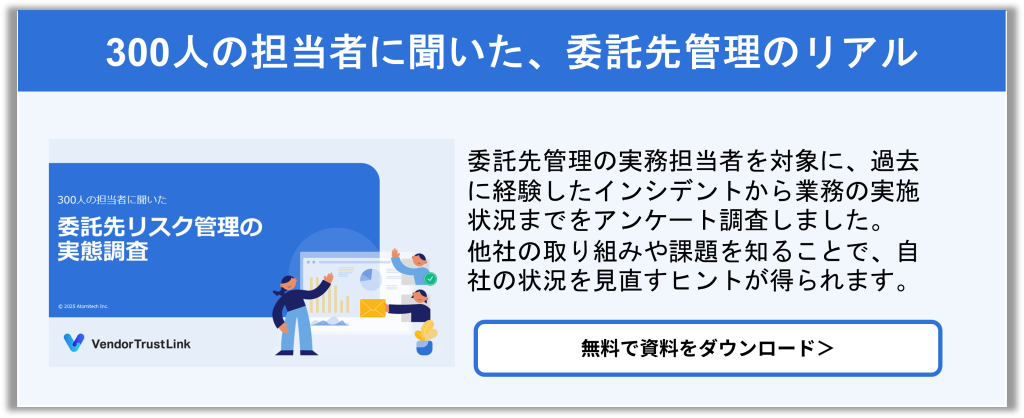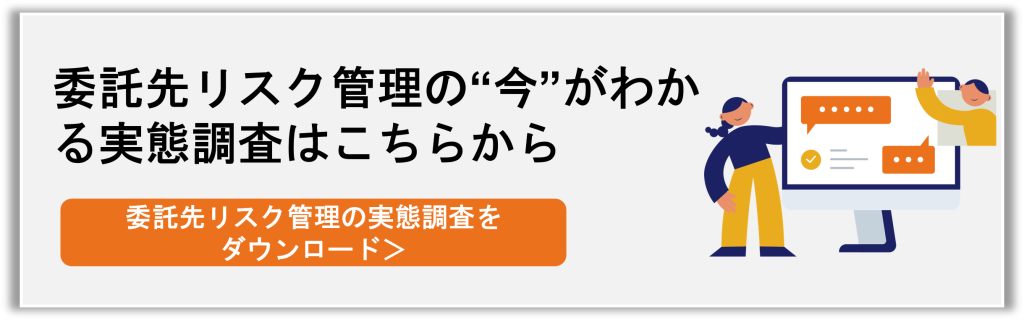2014年6月の労働安全衛生法により、業種や事業規模を問わず、リスクアセスメントの対象物を取り扱うすべての事業者に、リスクアセスメントの実施が義務化されました。
本記事では、化学物質のリスクアセスメント実施義務化について詳しく解説します。
1. リスクアセスメントとは
リスクアセスメントとは、職場や作業環境における潜在的な危険や有害な要因を特定し、そのリスクを評価して適切な対策を講じるプロセスです。労働者の安全を確保し、事故や健康被害を未然に防ぐためには、リスクアセスメントが欠かせません。
2. 化学物質のリスクアセスメントとは
化学物質のリスクアセスメントとは、化学物質を取り扱う際に発生する可能性のある危険を評価し、そのリスクを低減するための措置を講じるプロセスです。リスクアセスメントを実施することで、作業者の安全と健康を確保し、環境への影響を最小限に抑えることができます。
化学物質は適切に管理されないと重大な健康被害を引き起こす可能性があるため、事前にリスクを評価し、適切な管理策を講じることが法令で義務付けられています。
2006年4月1日の労働安全衛生法改正ではリスクアセスメントの実施が努力義務とされていましたが、2014年6月の労働安全衛生法改正でリスクアセスメント対象物質を取り扱うすべての事業者にリスクアセスメントが義務化されました。
|
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
引用:労働安全衛生法28条の2 |
化学物質のリスクアセスメントが義務化された背景には、過去の化学物質による事故や健康被害が挙げられます。これらの事例から得られた教訓を基に、法律やガイドラインが整備され、企業に対してリスクアセスメントの実施が義務付けられるようになりました。特に、化学物質はその特性上、取り扱いを誤ると重大な事故につながるため、事前のリスク評価が欠かせません。
例えば、化学物質のリスクアセスメントでは、取り扱う化学物質の危険有害性を特定し、それに基づいてリスクを見積もります。さらに、具体的なリスク低減措置を考え、実行することが求められます。
■リスクアセスメントの対象物
リスクアセスメントの対象物とは、リスクアセスメントの実施が義務付けられている物質です。リスクアセスメントの対象となる物質の数は2025年4月1日時点で約1,600種類で、2026年の4月1日に行われる予定の追加分を加えると、約2300種類の物質がリスクアセスメント対象物となる予定です。
最新のリスクアセスメントの対象物については厚生労働省の職場のあんぜんサイトで確認でき、エクセルデータをダウンロードすることもできます。
【参考資料】
■リスクアセスメントの対象となる事業者
リスクアセスメントの対象となる事業者は、リスクアセスメントの対象物を取り扱うすべての事業者です。製造業や化学工業、建設業、小売業、サービス業など、業種や規模に関わらず実施する義務があります。なぜなら、化学物質は日常的に多くの業種で使用されており、その取り扱いによって従業員や周囲の環境にリスクが生じる可能性があるためです。
以下のような事業者においてもリスクアセスメントを実施する義務があります。
- 研究や分析等で化学品を少量だけ取り扱う事業者
- 少量多品種の化学物質を取り扱っている事業者
- 製造工程段階でリスクアセスメント対象物を生成する事業者
一方、ラベルに危険有害性の絵表示がある化学物質を扱っている場合でも、リスクアセスメント対象物に指定されていないのであればリスクアセスメントの実施義務があるとは限りません。
3. 化学物質を扱う事業者の義務
化学物質を扱う事業者には、リスクアセスメントを実施する義務だけでなく、以下の義務もあります。
- SDSの交付
- GHSに基づいたラベル表示
- 化学物質管理者の選任
これらの義務は、従業員の健康と安全を守るだけでなく、法令遵守の観点からも対応が必要です。以下で詳しく解説していきます。
■SDSの交付
化学物質を扱う事業者には、労働安全衛生法・化学物質排出把握管理法・毒物及び劇物取締法で定められた化学物質を譲渡・提供する際に、SDS(安全データシート)を相手方取引先に交付する義務があります。
|
前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
引用:労働安全衛生法57条の2 |
ただし、「一般消費者の生活の用に供される製品」については、SDSを交付する義務はありません。
「一般消費者の生活の用に供される製品」には以下のようなものが含まれます。
- 薬機法で定められている医薬品・医薬部外品・化粧品
- 農薬取締法に定められている農薬
- 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品
- 表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品
- 一般消費者のもとに提供される段階の食品
- 家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品
■GHSに基づいたラベル表示
化学物質を扱う事業者には、譲渡・提供する化学物質の容器や包装に、GHSに基づいたラベルを表示する義務があります。
|
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 一 次に掲げる事項 イ 名称 ロ 人体に及ぼす作用 ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
引用:労働安全衛生法57条 |
GHSとは、化学物質の危険性と有害性を国際的に統一した基準で表示するシステムです。ラベルには、化学物質の名称や危険性の象徴的なピクトグラム、注意喚起の言葉、危険有害性情報、予防措置情報などを表示します。
■化学物質管理者の選任
化学物質を扱う事業者には、化学物質管理者を選任する義務があります。
化学物質管理者とは、事業所内で化学物質の管理を統括し、安全な取り扱いを確保する役割を担う責任者です。選任された化学物質管理者は、化学物質のリスクアセスメントの実施や安全対策の策定を行います。
4. 化学物質のリスクアセスメントの実施方法
化学物質のリスクアセスメントは、以下の手順で実施します。
- 危険性・有害性の特定
- リスクの見積り
- リスク低減措置の実施
これらの手順を適切に行うことで、従業員や環境への影響を最小限に抑え、安全な作業環境を確保することができます。
■危険性・有害性の特定
化学物質には人体に有害なものや環境に悪影響を及ぼすものがあり、これらを見逃すと重大な事故につながる可能性があります。
危険性・有害性の特定を行うには、化学物質の物理的・化学的性質、健康への影響、取り扱い方法などが詳細に記載されている化学物質のSDS(安全データシート)を確認することが重要です。
また、危険性・有害性の特定では、化学物質の分類と表示に関する国際基準であるGHS(Globally Harmonized System)も活用します。GHSは、化学物質の危険性を統一的に表示するためのシステムです。ラベルに表示されているピクトグラムを確認することで、化学物質の危険性と有害性を特定することができます。
■リスクの見積り
リスクの見積りでは、化学物質が引き起こす可能性のある危険性や有害性がどの程度のリスクを持つかを評価します。
たとえば、ある化学物質が皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある場合、その化学物質がどの程度の頻度で使用されるか、またその使用環境がどれほど安全かを評価するわけです。リスクの発生確率と影響度を考慮することで、どのリスクを優先的に対処すべきかが明確になります。
リスクの見積りを行う際には、過去の事故データや専門家の意見を参考にすることも効果的です。また、リスクを定量的に評価するために、数値化されたデータを用いることもあります。例えば、事故発生の頻度を年間何件といった形で表したり、影響の大きさを金銭的損失や健康被害の程度で示したりします。
■リスク低減措置の実施
リスク低減措置とは、リスクの見積りで優先度が高いと評価されたリスクから危険性や有害性を最小限に抑えるための対策です。
具体的なリスク低減措置としては、化学物質の飛散や漏れを防ぐための設備や装置の導入などの物理的な防護策があります。例えば、換気装置の設置や防毒マスクや防塵マスクなどの保護具の使用によって、リスクを大幅に減少させることが可能です。
また、作業手順の見直しも重要です。作業者が化学物質を取り扱う際の手順を再評価し、安全な方法を確立したり、作業者への教育や訓練を実施したりすることが求められます。作業者が正しい知識を持ち、適切な手順で作業することで、リスクをさらに低減することが可能です。
5. リスクアセスメントの実施時期と体制
■いつリスクアセスメントを行うべきか
労働安全衛生法でリスクアセスメントの実施が義務付けられているのは以下のタイミングです。
- 対象物を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき
- 対象物を製造し、または取り扱う業務の作業方法や作業手順を新規に採用したり変更したりするとき
- 上記のほか、対象物による危険性または有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれがあったりするとき
以下のようなケースについては、指針で努力義務とされています。
- 労働災害発生時(過去のリスクアセスメントに問題があるとき)
- 過去のリスクアセスメント実施以降、機械設備などの経年劣化、労働者の知識経験などリスクの状況に変化があったとき
- 過去にリスクアセスメントを実施したことがないとき(施行日前から取り扱っている物質を、施行日前と同様の作業方法で取り扱う場合で、過去にRAを実施したことがない、または実施結果が確認できない場合)
【参考】
■実施体制の構築方法
リスクアセスメント実施体制の構築については、企業のトップがリスクアセスメントの重要性を理解し、全社的な取り組みとして推進することが重要です。化学物質のリスクアセスメントは組織全体での協力が不可欠なため、経営陣の支持が鍵となります。また、専門知識を持つ担当者を選任することも重要です。化学物質管理者や安全衛生推進者を中心に、リスクアセスメントを主導するチームを編成します。
また、社員全員がリスクアセスメントの意義を理解し、日常業務での安全意識を高めるための教育や研修を定期的に行うことも必要です。
6. リスクアセスメント義務化に関するよくある質問
■リスクアセスメントの義務は誰にある?
労働安全衛生法で定められたリスクアセスメントの対象物を取り扱うすべての事業者は、業種や規模に関係なくリスクアセスメントを実施する義務があります。以前は努力義務とされていましたが、2014年6月の労働安全衛生法改正ですべての事業者でリスクアセスメントが義務化されました。
■少量の化学物質でもアセスメントは必要?
少量の化学物質しか取り扱っていない事業者でも、リスクアセスメントを実施する必要があります。なぜなら、たとえ少量であっても化学物質が持つ危険性や有害性が消えるわけではなく、安全な作業環境を維持するためには、そのリスクを正確に評価することが求められるからです。例えば、揮発性の高い化学物質は少量でも空気中に拡散し、吸入による健康被害を引き起こす可能性があります。実際には少量でも、化学物質の取り扱い方法や保管方法、緊急時の対応策などを明確にし、作業者の安全を確保することが重要です。
【参考】
Q3-3.少量多品種の化学物質を取り扱っているが、全ての化学物質についてリスクアセスメントを実施しなければならないか。
7. まとめ
今回は、化学物質のリスクアセスメント実施義務化の背景や目的、具体的な実施方法について解説しました。
化学物質のリスクアセスメントが義務化された背景には、作業者の安全確保や環境保護といった社会的な要請があります。本記事で解説した化学物質のリスクアセスメント実施方法を参考に、職場での安全対策を見直してみましょう。
アトミテックでは、委託先リスク管理の担当者300名への調査結果をまとめた「委託先リスク管理の実態調査」を公開しています。ぜひ他社の取り組み状況や最新の傾向を知る参考になさってください。