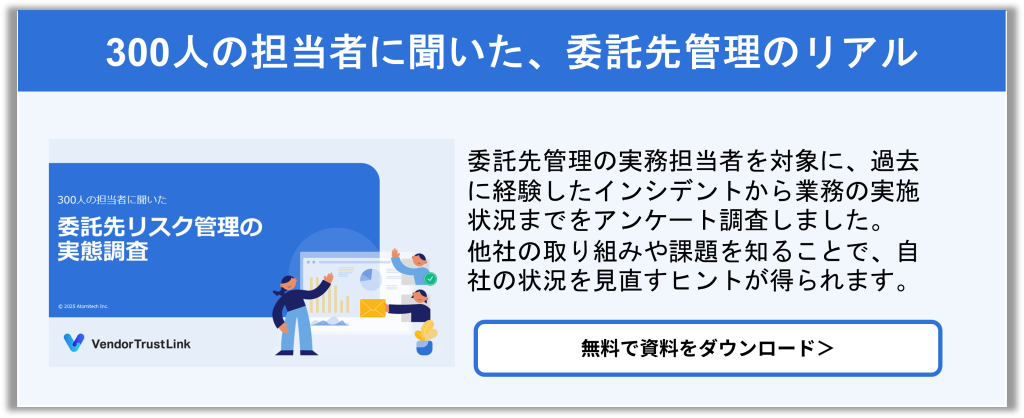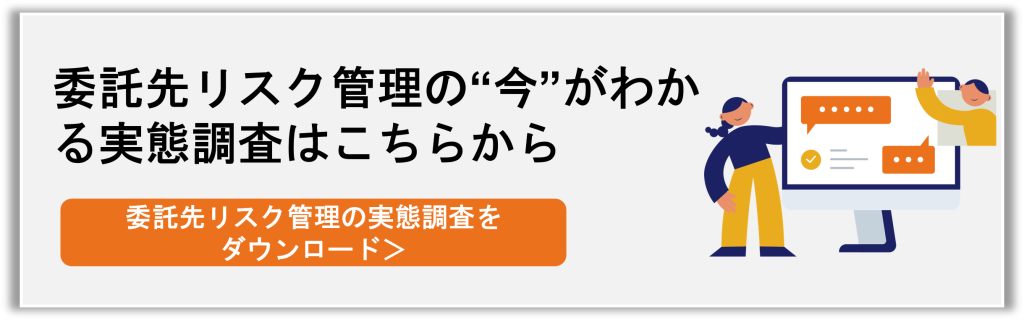特定の企業だけに取引を集中させている場合、取引相手が倒産したりトラブルが発生したりすることで自社も大きな影響を受けるリスクがあります。1社だけに依存するのではなく、複数の企業と取引してリスクを分散することが重要です。
本記事では、リスク管理における取引先分散のメリット・デメリットについて解説します。
1.一社依存とは
一社依存とは、企業が特定の取引先に対して売上や利益の大部分を依存している状態です。特定の取引先が経済的な問題に直面したり、関係が悪化したりすると、企業の経営において大きなリスクを伴う可能性があります。
一社依存が生じる背景には、特定の取引先との長期的な関係を重視するあまり、他の取引先を見つける努力が不足することがあります。また、特定の取引先が非常に大きな発注を行う場合、自然と依存度が高まることもあります。例えば、製造業では大手メーカーとの取引に依存することで、安定した売上を確保できる一方、そのメーカーの経営方針や市場の変化に左右されやすくなるわけです。
■取引依存度とは
取引依存度とは、特定の取引先に対する依存度を示す指標であり、特定の取引先が全体の売上に占める割合を指します。例えば、ある企業の売上の50%が一つの取引先から来ている場合、その企業は高い取引依存度を持つといえます。取引依存度が高いと、取引先の経営状況や市場の変動に大きく影響され、経営上のリスクが高まります。取引先が倒産した場合、企業の存続に直接的な影響を及ぼし、連鎖倒産に繋がる恐れもあります。
2.一社依存がもたらすリスク
■取引先の影響を受けやすくなる
特定の取引先に依存する企業は、その取引先の売上が全体の多くを占めることが多く、これが企業の経済的安定に直接影響します。例えば、ある企業が主要取引先からの売上が全体の70%を占めている場合、その取引先の業績悪化や契約終了は企業にとって致命的な打撃となるでしょう。対策として、売上の多様化を図り、新たな取引先を積極的に開拓することが求められます。
■取引先喪失時の経済的ダメージ
取引先を失った場合、企業にとって最も深刻な問題は経済的ダメージです。特に一社依存の状態にある企業は、その影響が顕著です。例えば、主要な取引先が突然契約を打ち切った場合、売上の大部分を失うことになります。このような状況では、資金繰りが悪化し、従業員の給与支払いが滞る可能性もあります。また、新たな取引先を探すための時間とコストがかかり、経営の安定を取り戻すのに時間がかかることもあります。
■交渉力の低下と不利な条件への妥協
主要な取引先に依存しすぎると、取引先の要求に対して強く出られず、結果として不利な契約条件を受け入れざるを得なくなることがあります。例えば、価格引き下げや納期の短縮といった無理な要求に対しても、取引を維持するために応じざるを得ない状況に陥るかもしれません。
3.取引先を分散させるメリット
取引先を分散させるメリットは以下の2つです。
- 取引先で発生したリスクの影響が少なくなる
- 競争力が向上する
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
■取引先で発生したリスクの影響が少なくなる
取引先を分散させる1つ目のメリットは、取引先で発生したリスクの影響が少なくなることです。
製造する商品を納品する企業の場合、納品先が倒産してしまうと商品を納品できなくなり、資金を回収できなくなります。納品できないことで商品を保管する場所を新たに確保したり、別の納品先を探したりするといった対応も必要です。納品先が1社だけの場合、連鎖倒産に繋がる可能性もあります。このようなリスクは、納品先だけでなく資源の調達先や商品の配送を依頼する会社、業務の委託先などにも当てはまるリスクです。
一方、複数の取引先と取引している場合、取引先でなんらかのトラブルが発生した場合においても、自社への影響を最小限に抑えることができます。取引先が多いほど、取引先で発生したリスクの影響は少なくなるわけです。
■競争力が向上する
取引先を分散させる2つ目のメリットは、競争力が向上することです。
納品先が1社だけの場合、営業担当者は新規取引先を探す必要がなく、納品先との取引だけに専念することができます。しかし、取引を継続してもらうことだけを意識していると、新たな製品の開発や新規分野の開拓などがおろそかになり、いつのまにか競争力が低下する恐れがあります。
一方、複数の企業と取引するためには、取引先からの要望に応えられるだけの技術力や販売力を身に付けることが必要です。その過程で企業としての競争力が向上するため、事業の存続・拡大に繋がります。
4.取引先を分散させるデメリット
取引先を分散させるデメリットは以下の2つです。
- スケールメリットが減少する
- 業務効率が低下する
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
■スケールメリットが減少する
取引先を分散させる1つ目のデメリットは、スケールメリットが減少することです。
仕入先が1社だけの場合、複数の取引先から仕入れる場合より仕入れる量が増加するため、仕入単価が低下します。他の企業と取引していないことを理由に、有利な条件を提示されることもあるでしょう。
一方、複数の取引先から仕入れる場合だと、将来的に取引金額が増加する可能性が低く、シェア率が高くなる見込みも少ないため、厳しい条件が提示される場合があります。
■業務効率が低下する
取引先を分散させる2つ目のデメリットは、業務効率が低下することです。
取引先を分散させる場合、取引先が1社の場合と比べて経理や営業担当者の負担が大きくなり、業務効率の低下に繋がります。
5.取引先を分散させるポイント
取引先を分散させるポイントは以下の2つです。
- 取引先ごとの利益貢献度を確認する
- 取引先のリスク管理を行う
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
■取引先ごとの利益貢献度を確認する
取引先を分散させる1つ目のポイントは、取引先ごとの利益貢献度を確認することです。
取引先ごとの利益貢献度は、相乗積を活用することで確認できます。
相乗積の計算式は以下の通りです。
相乗積(%)=売上高比率×粗利益率
|
取引先 |
売上高比率 |
粗利益率 |
相乗積 |
|---|---|---|---|
|
取引先A |
50% |
6% |
3% |
|
取引先B |
30% |
20% |
6% |
|
取引先C |
20% |
30% |
6% |
上記の例の場合、取引先Bと取引先Cは取引先Aと比べて相乗積が倍になっており、利益貢献度が高いことが分かります。
売上高の割合が高くても利益貢献度が低い場合には、新規取引先を増やす方が利益を確保しやすくなります。
■取引先のリスク管理を行う
取引先を分散させる2つ目のポイントは、取引先や委託先のリスク管理を行うことです。
取引先や委託先のリスク管理においては、自社だけでなく取引先で発生するリスクを管理することも重要となります。不正アクセスやコンプライアンス違反、製品の不備、ハラスメントといった、委託先で発生したトラブルによって自社の経営が悪化したり倒産したりしないようにする必要があるからです。
取引先で発生する主なリスクは以下の通りです。
- コンプライアンスリスク
- レピュテーションリスク
- セキュリティリスク
- 事業継続リスク
- オペレーショナルリスク
上記のリスクが発生する可能性がどのくらいあるのか、発生した場合にどのくらい影響を受けるのかを分析し、リスクが発生した後にどのような対応をすべきなのか事前に計画を立案します。
【関連記事】
委託先管理とは?目的や必要な理由、実施する際のポイントを解説
6.まとめ
今回は、リスク管理における取引先分散のメリット・デメリットについて解説しました。
仕入や販売、物流、業務委託などを特定の取引先に依存しすぎていると、取引先で倒産や廃業、不正アクセスなどが発生した際に、自社が大きな影響を受けてしまいます。
取引先を分散するメリット・デメリットを理解したうえで、意図的に取引先を分散することも検討してみましょう。
アトミテックでは、委託先リスク管理の担当者300名への調査結果をまとめた「委託先リスク管理の実態調査」を公開しています。ぜひ他社の取り組み状況や最新の傾向を知る参考になさってください。