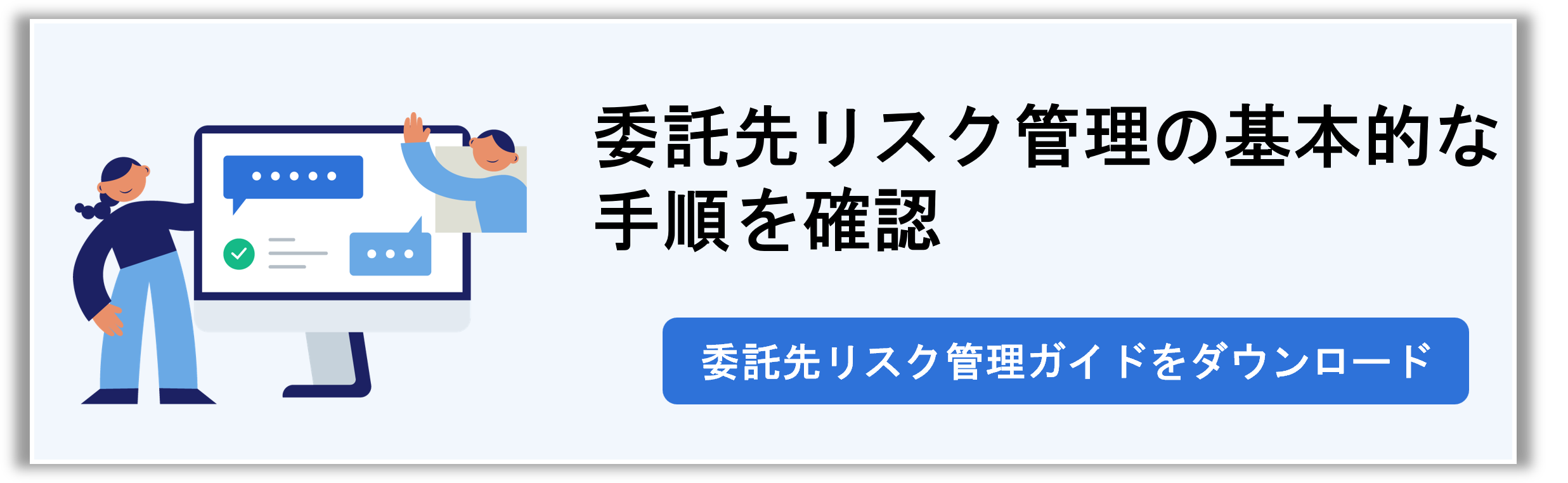サステナブルなサプライチェーンの構築を目指し、ESG経営に取り組むサプライチェーン企業が増加しています。環境問題や人権問題、社会問題を意識しながら経営することは、サプライチェーンマネジメントとしても重要です。
本記事では、サプライチェーンでESG経営が重視されている理由やサプライチェーンがESG経営を行うメリット、サプライチェーンにおけるESGの具体的な取り組み、ESGを意識したサプライチェーン企業の取り組み事例について解説します。
1. ESGとは
ESGとは、Environment(環境)・Social(社会)・Governance(ガバナンス・企業統治)の頭文字を取った用語です。
環境・社会・ガバナンスの3つの要素を考慮することで、持続可能な社会の実現を目指します。具体的には、環境面では気候変動対策を行い、社会面では労働環境の改善を図り、ガバナンス面では透明性のある経営を実践することが求められます。ESGは、企業の社会的責任を果たすための指針として多くの企業や投資家に注目されています。
ESGが重視される理由は、環境問題や社会課題が深刻化する中で、企業が長期的な視点で持続可能な成長を遂げるためには、単に利益追求だけでなく、社会や環境への配慮が必要だからです。ESGに取り組むことで、企業はリスク管理を強化し、信頼性を向上させることができます。また、ESGを重視する投資家は、持続可能なビジネスモデルを持つ企業を選別し、長期的なリターンを期待しています。
■環境(E:Environment)の役割
企業が環境に配慮した活動を行うことで、企業は環境負荷を減らし、地球温暖化や自然資源の枯渇といった問題に対処することができます。具体的には、温室効果ガスの排出削減、資源の効率的利用、廃棄物の削減などが挙げられます。
環境への配慮は、企業にとっても大きなメリットがあります。たとえば、エネルギー効率を改善することでコストを削減できるほか、環境に優しい製品やサービスは消費者からの支持を得やすくなります。「環境に配慮した企業の製品を選びたい」と考える消費者が増えているため、環境対策を行うことは企業の競争力を高める要因となるでしょう。
■社会(S:Social)の重要性
企業が従業員に対して安全で健康的な職場を提供することは、従業員のモチベーションを高め、生産性の向上につながります。
また、地域社会との良好な関係構築は、企業のブランドイメージを向上させ、顧客や投資家からの信頼を得ることができます。例えば、企業が地域の教育支援や環境保護活動に積極的に参加することで、地域からの信頼を得られ、結果として企業の競争力を高めることが可能です。さらに、社会的な問題に対する取り組みは、企業のリスク管理の一環としても重要です。社会問題が企業の経営に悪影響を及ぼす可能性があるため、これに対処することで、長期的なリスクを軽減できます。
■ガバナンス(G:Governance)の意義
ガバナンスとは、企業がどのように経営され、意思決定が行われるかの枠組みを指します。具体的には、経営陣の監督体制、リスク管理、透明性のある情報開示、倫理的な行動の促進などが含まれます。
ガバナンスの強化は、投資家や消費者からの信頼を得るために不可欠です。例えば、透明性のある情報開示は、企業がどのように運営されているかを明確にし、投資家に安心感を与えます。また、倫理的な行動の促進は、企業の社会的責任を果たすために重要です。
■ESG経営とは
ESG経営とは、環境・社会・ガバナンスの観点を企業経営に統合するアプローチのことです。企業が持続可能な成長を目指すために、環境負荷の低減や社会的責任の果たし方、経営の透明性を重視することが求められます。これにより、企業は単なる利益追求にとどまらず、長期的な視点での価値創造を目指します。サプライチェーンにおいては、ESG経営を行うことでサステナブルなサプライチェーンの構築が可能です。
ESG経営が注目される理由は、社会全体の価値観の変化にあります。消費者や投資家が環境や社会問題に対する意識を高める中、企業もこれらの期待に応える必要があります。例えば、企業は環境負荷の低い製品開発を進めることで競争力を高めることができます。また、ガバナンスの強化により、企業の信頼性を向上させることも可能です。
ESG経営のもう一つの利点は、リスク管理の強化です。例えば、環境規制の強化や社会的な批判を受けるリスクを事前に把握し、対応策を講じることで、企業は経営の安定性を保つことができます。
■ESG投資とは
ESG投資とは、企業の環境・社会・ガバナンスに関する取り組みを評価し、それに基づいて投資を行う手法のことです。近年、企業の持続可能性や社会的責任が注目される中で、ESG投資はますます重要視されています。
ESG投資の背景には、気候変動や社会問題への関心の高まりがあります。投資家は企業の財務的な指標だけでなく、環境への配慮や労働環境の改善、企業統治の透明性などを評価することで、投資すべき企業なのかを判断しようとしています。
ESG投資には、ネガティブ・スクリーニングやポジティブ・スクリーニングといった手法があります。ネガティブ・スクリーニングは、特定の基準に満たない企業を除外する方法であり、ポジティブ・スクリーニングは、ESGに対して積極的に取り組んでいる企業を選ぶ方法です。
■CSRとの違い
ESGとCSRの違いは、取り組みに対する企業の考え方です。
CSR(Corporate Social Responsibility)は、利害関係者である顧客や従業員、株主、地域社会に対する企業の社会的責任を意味します。環境問題や人権問題、社会問題といった社会的責任に対して自社が取り組んでいることを利害関係者へアピールすることが、CSRの目的です。
一方、ESGは環境問題や人権問題、社会問題を解決すること自体が自社のビジネスであり、課題の解決によって利益を確保できるようにビジネスを設計します。
【関連記事】
CSR調達とは?大手企業におけるCSR調達及び委託先管理の実施状況を紹介
■サステナブルなサプライチェーンとは
サステナブルなサプライチェーンとは、自社だけでなくサプライチェーン全体が事業を継続できる状態に維持することです。持続可能なサプライチェーンとも呼ばれます。
自社あるいはサプライチェーン企業で環境問題や人権問題、社会問題が発生すると、サプライチェーンのプロセスがストップするため、サプライチェーンは事業は継続できません。
サプライチェーン全体で環境問題や人権問題、社会問題を意識することで、リスクの発生を未然に防ぎ、発生した場合においても早期対応することができ、事業を継続できるようになるわけです。
【関連記事】
2. サプライチェーンでESG経営が重視されている理由
サプライチェーンでESG経営が重視されている理由は以下の2つです。
- 社会問題への取り組みが求められている
- 投資家の評価指標になっている
それぞれの理由について詳しく解説します。
■社会問題への取り組みが求められている
サプライチェーンでESG経営が重視されている1つ目の理由は、社会問題への取り組みが求められていることです。
近年では、化石燃料を使った火力発電・森林伐採によるCO2排出量の増加といった環境問題に注目が集まっています。児童労働や時間外労働などの人権問題も、社会的に注目されている課題です。通常の企業活動が環境に対してマイナスの影響を与えることもあるため、企業は課題解決に向けて具体的に取り組むことが求められています。
■投資家の評価指標になっている
サプライチェーンでESG経営が重視されている2つ目の理由は、投資家の評価指標になっていることです。
近年では、従来のように企業の利益や所有する資産などから投資先を選ぶのではなく、投資の対象となる企業が環境問題や人権問題、社会問題に対してどのように取り組んでいるのかを重視して投資先を選ぶESG投資が増加しています。
環境問題や人権問題、社会問題に取り組むことでESG投資の対象となるため、ESG経営を目指す企業が増加しているわけです。
3. サプライチェーンがESG経営を行うメリット
サプライチェーンがESG経営を行うメリットは以下の3つです。
- 競合他社との差別化やイメージアップに繋がる
- 資金を確保しやすくなる
- 優秀な人材を確保しやすくなる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
■競合他社との差別化やイメージアップに繋がる
サプライチェーンがESG経営を行う1つ目のメリットは、競合他社との差別化やイメージアップに繋がることです。
いつでも、どこからでも情報を入手できる現代においては、競合他社との差別化が重視されています。似たようなサービスや商品を提供する、価格で勝負するだけでは、競合他社との違いを明確にできず、自社の製品を選んでもらえないかもしれません。自社製品の知名度を上げるために高額な広告費がかかり、利益を圧迫することもあるでしょう。
一方、ESG経営を行えば競合他社との差別化やイメージアップに繋がり、広告費を削減することができるため、利益を確保しやすくなるわけです。
■資金を確保しやすくなる
サプライチェーンがESG経営を行う2つ目のメリットは、資金を確保しやすくなることです。
前述したように投資家は企業がESG経営をしているかも評価も対象としており、ESG経営を行うことで投資の対象になりやすくなります。
■優秀な人材を確保しやすくなる
サプライチェーンがESG経営を行う3つ目のメリットは、優秀な人材を確保しやすくなることです。
求職者の中には、企業としての知名度や賃金よりも、企業の経営理念や労働環境を重視して就職先を選ぶ人もいます。ESG経営を行うことで環境問題や人権問題、社会問題に対する自社の姿勢を明確にアピールでき、労働環境や将来性に不安を感じる求職者からも応募してもらえるようになるわけです。
4. サプライチェーンにおけるESGの具体的な取り組み
サプライチェーンにおけるESGの具体的な取り組みは以下の2つです。
- 脱炭素化
- サステナブル調達・CSR調達
それぞれの取り組みについて詳しく解説します。
■脱炭素化
効率良く脱炭素化を進めるために、サプライチェーンでは個別の企業で排出量を削減するだけでなくサプライチェーン排出量を削減することが求められています。
サプライチェーン排出量とは、サプライチェーンの一連の流れの中で発生する温室効果ガスも含めた温室効果ガスの排出量です。
具体的には、サプライヤーに対してCO2削減を求める、CO2を排出しない製品の開発、生産・物流のDX化といった脱炭素化に向けた取り組みが行われています。
【関連記事】
サプライチェーン全体での脱炭素化が必要な理由と進めるメリットを解説
■サステナブル調達・CSR調達
サステナブル調達・CSR調達とは、環境や人権などの国際的な社会問題に配慮して原材料を調達することです。
環境問題や人権問題への社会的な関心が高くなっていることや、社会情勢の変化による価格高騰に対応するために、サステナブル調達・CSR調達を行う企業が増加しています。
具体的には、自然資源の違法な取引・採取・漁獲を排除する、児童労働・強制労働が行われている国からは調達しない、トレーサビリティの確立といった取り組みが行われています。
【関連記事】
CSR調達とは?大手企業におけるCSR調達及び委託先管理の実施状況を紹介
サステナブル調達とは?求められている理由や進め方、企業事例を解説
5. ESGを意識したサプライチェーン企業の取り組み事例
■NTTグループ
NTTグループでは、自然災害やパンデミック、環境問題、人権問題、不正アクセスといった世界的規模の課題への適切な対応と調達に関する基本方針に基づき、「NTT グループサステナビリティ憲章」を制定しました。
|
Environment(環境) |
行政に対する環境許可と報告 製品含有化学物質の管理 化学物質の管理 環境への影響の最小化(廃水・汚泥・排気・騒音・振動など) エネルギー消費及び温室効果ガスの排出削減 製品アセスメントの実施による環境負荷低減 資源の有効活用と廃棄物管理 生物多様性保全 サプライチェーンにおける環境調査の実施 |
|
Social(社会) |
強制的な労働の禁止 非人道的な扱いの禁止 児童労働の禁止、若年労働者への配慮 差別の禁止 適切な賃金と手当 労働時間 結社の自由、団体交渉権 サプライチェーンにおける人権デューデリジェンスの実施 高い倫理観に基づくテクノロジーの推進 |
|
Governance(ガバナンス) |
汚職や違法な政治献金の防止、不適切な利益供与及び受領の禁止 優越的地位の濫用の禁止 公正なビジネスの遂行 知的財産の尊重 適切な輸出入管理 不正行為の予防 責任ある鉱物調査とデューデリジェンスの実施 |
参考資料:NTTグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン
■豊田通商グループ
豊田通商グループでは、人権や労働環境、自然環境に配慮したサステナブルなサプライチェーンの構築に向けて「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」を策定し、サプライヤーへの周知と実践を行っています。
|
Environment(環境) |
地球環境への配慮 |
|
Social(社会) |
人権の尊重 強制労働・児童労働・不当な低賃金労働の防止 差別の撤廃 |
|
Governance(ガバナンス) |
公正な取引および腐敗防止の徹底 |
■東レグループ
東レグループでは、地球温暖化防止や環境保護、人権尊重、労働環境改善などの課題解決と安定かつ持続可能な調達のために、品質や供給安定性に加えて、倫理的で環境や社会、人権に配慮したサプライチェーンを実現することを「東レグループCSR調達方針」で宣言しています。
|
Environment(環境) |
適正な輸出入管理 責任ある原材料調達 境マネジメント 環境マネジメント 温室効果ガスの排出削減 環境への影響の最小化 省資源・廃棄物管理 化学物質管理 生物多様性への配慮 |
|
Social(社会) |
職務上の安全管理 労働衛生管理 |
|
Governance(ガバナンス) |
法令遵守 競争法の遵守 腐敗防止・贈収賄の禁止 利益相反行為の禁止 機密情報・個人情報の保護 内部通報制度および通報者保護 |
参考資料:持続可能なサプライチェーンの構築 – サステナビリティ
6. まとめ
今回は、サプライチェーンにおけるESG経営について解説しました。
重視されている理由やメリット、具体的な取り組みは以下の通りです。
|
重視されている理由 |
|
|
メリット |
|
|
具体的な取り組み |
|
本記事で紹介した取り組み事例を参考に、ESG経営に取り組んでみましょう。
アトミテックでは、委託先リスク管理の手順をまとめた委託先リスク管理ガイドを公開しています。ぜひ自社の委託先管理の参考になさってください。