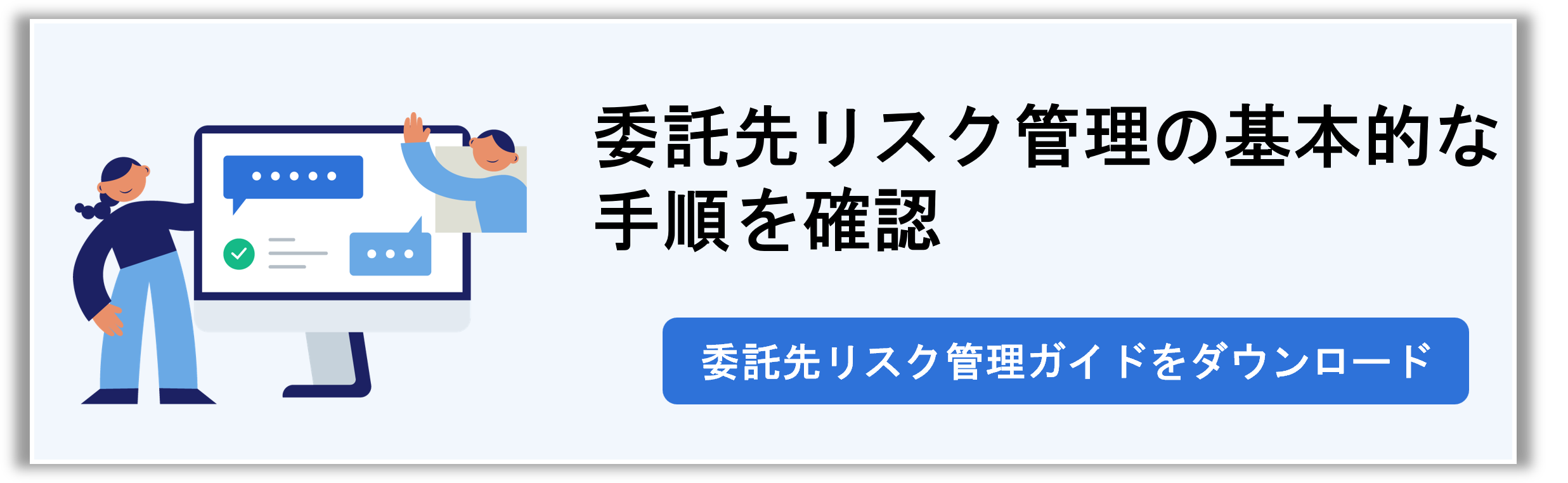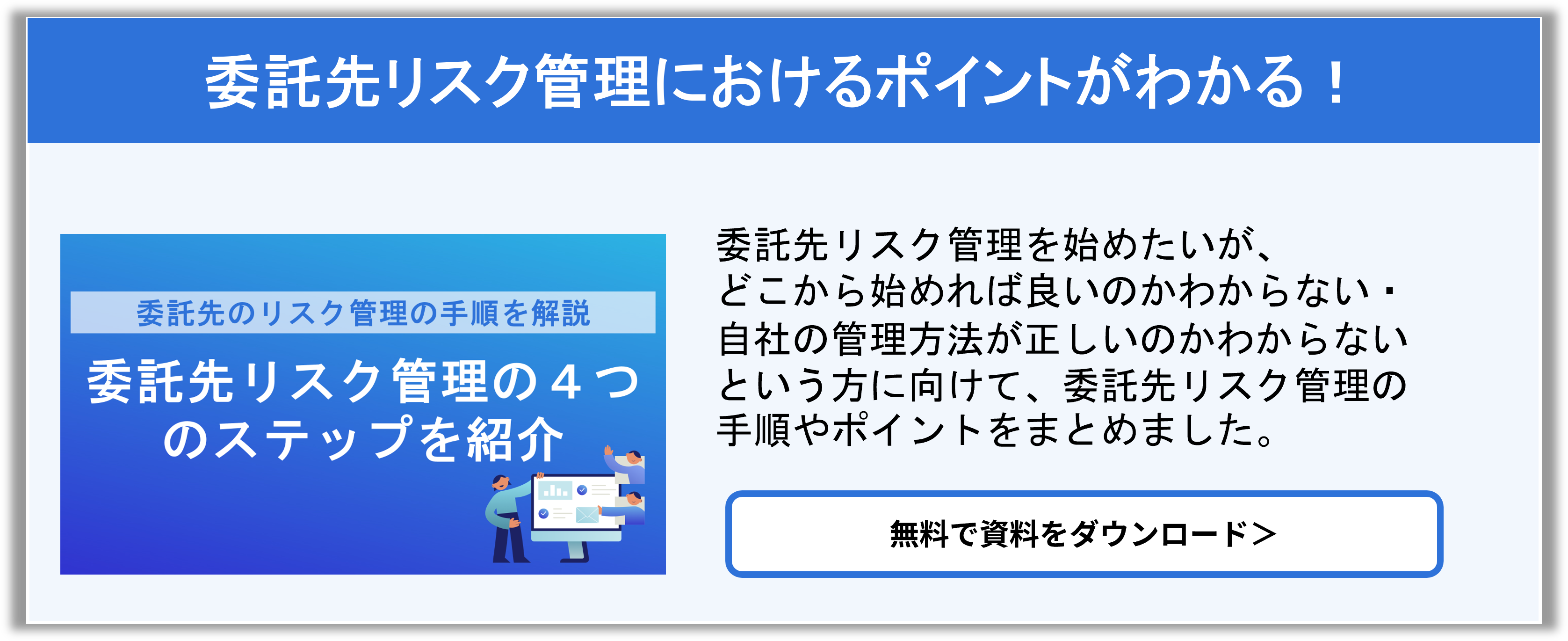近年では脱酸素化に取り組む企業が増加していますが、個別の企業だけでなくサプライチェーン全体としても脱炭素化を進める必要があるのか、脱炭素化を進めることでどのようなメリットがあるのか疑問に感じているのではないでしょうか?
本記事では、サプライチェーン全体での脱炭素化が必要な理由とサプライチェーン全体で脱炭素化を進めるメリット、脱炭素化を進める企業の事例について解説します。
1.そもそも脱炭素化とは
脱炭素化とは、二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化の進行を抑制する取り組みを指します。持続可能な未来を築くために必要不可欠なプロセスであり、企業や個人、政府が協力して進めるべき重要な課題です。脱炭素化を進めることで、環境への負荷を軽減し、エネルギーの効率的な利用を促進することが期待されます。
例えば、パリ協定では世界各国が温室効果ガスの削減目標を設定し、地球の平均気温上昇を2℃未満に抑えることを目指しています。
■脱炭素化が注目される理由
脱炭素化が注目される理由は、地球温暖化の進行と、それに伴う気候変動の深刻化にあります。地球の平均気温が上昇し続けると、異常気象や海面上昇が引き起こされるため、これを抑制するための取り組みが急務となっています。特に、温室効果ガスの主要な原因である二酸化炭素(CO2)を削減することが重要です。
また、国際的な合意であるパリ協定に基づき、多くの国がCO2排出量を削減する目標を掲げています。化石燃料に依存したエネルギー供給は資源の枯渇や価格変動のリスクが伴うため、再生可能エネルギーの導入が進められているわけです。
企業においても、脱炭素化は競争力を維持するための重要な要素です。消費者の環境意識が高まる中、環境に配慮した企業活動が求められています。脱炭素化の取り組みは、企業のブランド価値を高めるだけでなく、コスト削減や新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。このように、脱炭素化は地球環境の保護と経済活動の持続可能性を両立させるために欠かせない取り組みなのです。
■温室効果ガス削減の必要性
温室効果ガス削減は、地球温暖化を防ぎ、持続可能な未来を築くための重要な取り組みです。
温室効果ガスは主に二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)などで構成され、地球の気温を上昇させる原因となります。特に産業革命以降、人間の活動によってこれらのガスの排出量が急増し、地球温暖化が進行しています。
温室効果ガスの削減は、こうした気候変動の影響を緩和するために不可欠です。具体的には、再生可能エネルギーの利用拡大や省エネ技術の導入、さらには新しい技術開発が求められます。また、企業や個人が温室効果ガス削減に取り組むことで環境への負荷を減らし、社会全体の持続可能性を高めることができます。企業においてはサプライチェーン全体での排出量を見直し、効率的な資源利用を推進することで、経済的な利益を得ることも可能です。
■カーボンニュートラルとの違い
カーボンニュートラルと脱炭素化はどちらも地球環境の保護を目指す取り組みですが、その意味やアプローチには違いがあります。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量を均等にし、実質的な排出ゼロを目指すことを指します。具体的には、植林や再生可能エネルギーの利用などで排出した二酸化炭素を相殺する方法です。一方、脱炭素化は、二酸化炭素の排出そのものを削減することに焦点を当てています。例えば、化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーへの転換を進めることが含まれます。カーボンニュートラルは短期的な目標として、脱炭素化は長期的な視点で進めることが推奨されます。
■脱炭素経営とは
脱炭素経営とは、企業が事業活動において排出する温室効果ガスを削減し、持続可能な社会を実現するための取り組みを指します。具体的には、エネルギー使用の効率化、再生可能エネルギーの導入、製品やサービスのライフサイクル全体での環境負荷の低減が含まれます。脱炭素経営が注目される背景には、地球温暖化の進行や気候変動の影響が深刻化していることがあります。
また、企業が脱炭素経営を進めることで、コスト削減や新たなビジネスチャンスの創出につながる可能性もあります。例えば、エネルギー効率を高めることで、電力消費量を減少させ、結果的に経費を削減できます。さらに、環境に配慮した製品やサービスは、消費者からの支持を得やすく、企業のブランド価値向上にも寄与します。
2.サプライチェーン全体での脱炭素化が必要な理由
サプライチェーン全体での脱炭素化が必要な理由は以下の3つです。
- サプライチェーン全体の排出量を削減する必要がある
- SBT(温室効果ガス排出削減目標)はサプライチェーン全体での削減を求めている
- 日本政府もサプライチェーン全体での脱炭素化を推進している
それぞれの理由について詳しく解説します。
サプライチェーンについては下記の記事で詳しく解説しています。
■サプライチェーン排出量を削減する必要がある
サプライチェーン全体で脱炭素化を進めることが求められているのは、効率良く脱炭素化を進めるためには、個別の企業で排出量を削減するだけでなくサプライチェーン排出量を削減する必要があるからです。サプライチェーン排出量は、サプライチェーンに関わる個別の企業から発生する温室効果ガスの排出量だけでなく、サプライチェーンの一連の流れの中で発生する温室効果ガスも含めた排出量を指します。
たとえば、製造業が脱炭素化を行う場合、自社の製造作業で発生する温室効果ガスを削減することは可能ですが、自社が直接関与しない原材料の調達や製品の輸送、販売、廃棄で発生する温室効果ガスを削減することは容易ではありません。一方、サプライチェーン全体で脱炭素化を進めれば、原材料の調達から製造、輸送、販売、廃棄といった一連の工程で発生する温室効果ガスの排出量を削減できるわけです。
■SBTはサプライチェーン全体での削減を求めている
企業による温室効果ガスの削減目標であるSBTは、個別の企業が排出する温室効果ガス(Scope1)を削減するだけでなく、Scope2・Scope3も含めたサプライチェーン全体での削減を求めています。SBPとは、パリ協定が合意した温室効果ガス排出削減目標です
SBTiによるSBT認定を目指す場合には、サプライチェーン全体での脱炭素化への取り組みが重要です。SBTiとは、WWF、CDP、世界資源研究所(WRI)、国連グローバル・コンパクトにより設立された共同イニシアティブです。
SBTが定める認定基準
- 企業全体(子会社含む)のScope1及び2をカバーし、すべてのGHGが対象
- 基準年はデータが存在する最新年とすることを推奨
- 目標年は公式提出時点から最短5年、最⾧15年以内
- 最低でも2℃を十分に下回る水準に抑える削減目標を設定しなければならない。さらに、1.5℃目標を目指すことを推奨する。
- Scopeを複数合算(例えば、1+2、または1+2+3)した目標設定が可能。ただし、Scope1+2はSBT水準を満たすことが前提。
- 他者のクレジットの取得による削減、もしくは削減貢献量は、SBT達成のための削減に算入できない
参考資料:SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック「環境省」
「Scope」については後述します。
■日本政府もサプライチェーン全体での脱炭素化を推進している
日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現させることを目指しており、環境省が実施する「脱炭素経営による企業価値向上促進プログラム」では、以下のようなサプライチェーン全体での脱炭素の取り組みを推進しています。
- SBTやRE100(※1)などの目標設定の支援
- SBTやRE100などの目標に向けて削減行動の支援
- TCFD(※2)に沿った気候変動リスク・チャンスを織り込む経営の支援
参考資料:環境省 脱炭素経営による企業価値向上促進プログラムについて「環境省」
※1 RE100:事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブ
※2 TCFD:各企業の気候変動への取り組みを明確に開示する国際組織
3.サプライチェーンの脱炭素化の取り組みで重要な「Scope」
「Scope」とは、温室効果ガスの排出量を測定する範囲です。サプライチェーンで発生する温室効果ガスの排出量を正確に把握するために、Scope1・Scope2・Scope3の3つに分類されています。
|
Scope1 |
事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、⼯業プロセス) |
|
Scope2 |
他社から供給された電気、熱・蒸気を、自社で使⽤した際に伴う間接排出 |
|
Scope3 |
Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) |
サプライチェーンでは、Scope1・Scope2・Scope3を合計した排出量がサプライチェーン全体の排出量になります。
Scope1・Scope2については自社で排出量を把握したり削減したりすることができますが、Scope3については自社以外の企業から排出される温室効果ガスなので、自社が具体的な数値を把握するのは困難です。
サプライチェーンで発生する温室効果ガスの排出量をScope1・Scope2・Scope3の3つに分類することで全体像を把握しやすくなり、目標値を設定したり削減計画を立てたりすることが可能になります。
4.サプライチェーン全体で脱炭素化を進めるメリット
サプライチェーン全体で脱炭素化を進めることで、サプライチェーンの各企業では企業としての価値が高く評価されるようになり、競合企業との差別化に繋がります。
サプライチェーン全体で脱炭素化を進めるメリットは以下の3つです。
- ESG投資の対象になりやすくなる
- ビジネスチャンスが増加する
- 優秀な人材を確保しやすくなる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
■ESG投資の対象になりやすくなる
サプライチェーン全体で脱炭素化を進める1つ目のメリットは、ESG投資の対象になりやすくなることです。
ESG投資とは、売上高や利益、保有資産といった財務情報だけでなく、環境問題や労働問題、人権問題に対して取り組んでいるか、適切に企業統治が行われているかを重視して行われる投資です。Environment・Social・Governanceの頭文字を取ってESG投資と呼ばれています。
脱炭素化は環境問題に対する重要な取り組みなので、サプライチェーン全体で脱炭素化を進めていると、ESG投資の対象になりやすくなるわけです。
【関連記事】
サプライチェーンでESG経営が重視されている理由やメリット、事例を解説
■ビジネスチャンスが増加する
サプライチェーン全体で脱炭素化を進める2つ目のメリットは、ビジネスチャンスが増加することです。
近年ではCSR調達やサステナブル調達、グリーン調達を行う企業が増加しており、環境問題への取り組みが不足していると、取引先を選定する際に除外されてしまう恐れがあります。また、環境問題は社会的な関心も高くなっており、環境に配慮していない製品やサービスだと、一般消費者からも敬遠されてしまうかもしれません。
一方、脱炭素化を進めていると企業のイメージアップや競合他社との差別化ができ、新規顧客を獲得しやすくなるわけです。
■優秀な人材を確保しやすくなる
サプライチェーン全体で脱炭素化を進める3つ目のメリットは、優秀な人材を確保しやすくなることです。
前述した投資家と同様に、求職者も環境問題や労働問題、人権問題に対する取り組みを重視して企業を選定しています。SDGsや環境問題、持続可能性といったテーマはSNSやWEBサイトで取り上げられる機会が多く、若い世代からも注目されているからです。
約100カ国で活動している環境保全団体のWWFジャパンが実施した調査では、気候変動問題や環境問題、エネルギー問題に対して関心を持つ就活生は50%以上を占めています。
参考資料:就活のカギは「環境」? 学生は企業の取り組みをどう見ているか「WWFジャパン」
脱炭素化を進めることで就職先の候補になりやすくなり、人材確保においても有利になるでしょう。
5.脱炭素化を進めるサプライチェーン企業の事例
■トヨタ自動車株式会社
2050年カーボンニュートラル実現を目指すトヨタ自動車株式会社は、2015年10月に以下の6つのチャレンジを掲げた「トヨタ環境チャレンジ2050」を公表しました。
- ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ
- 新車CO2ゼロチャレンジ
- 工場CO2ゼロチャレンジ
- 水環境インパクト最小化チャレンジ
- 循環型社会・システム構築チャレンジ
- 人と自然が共生する
- 未来づくりへのチャレンジ
サプライチェーン排出量の削減に向けた取り組みとして、主要部品メーカーに対して年間3%のCO2削減を目標とすることを求めています。
参考資料:Toyota’s Views on Climate Public Policies 2022
■鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社は、建材メーカーや発注者などの関係他社との協働により、施工現場を中心に主体的な削減活動を実施しています。
サプライチェーン排出量の削減に向けた取り組みは以下の通りです。
- 低炭素建材の開発・使用
- ZEB(※3)の普及・拡大
参考資料:脱炭素 | サステナビリティ
※3 ZEB:Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称
■東洋紡株式会社
繊維・化成・バイオ・医薬などの開発・製造を行う東洋紡株式会社は、自社の活動に関連するサプライチェーン全体のGHG(※4)排出量の削減を進め、「事業活動における温室効果ガス排出量を2050年度までにネットゼロとすること」を目標としています。
サプライチェーン排出量の削減に向けた取り組みは以下の通りです。
- VOC回収装置(※5)へ新技術や省エネ技術を導入
- ユーティリティ(蒸気、電気等)使用量を抑制
- 事業所の最寄り港を活用することによる輸送距離の短縮
- 荷物を効率的に積み合わせ
- まとめて輸送することによる車両の走行台数削減
参考資料:気候変動 | サステナビリティ
※4 GHG:二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの排出量
※5 VOC回収装置:VOC(揮発性有機化合物)を回収、精製、燃焼処理する装置
6.まとめ
今回は、サプライチェーン全体での脱炭素化について解説しました。
サプライチェーン全体での脱炭素化が必要な理由とサプライチェーン全体で脱炭素化を進めるメリットは以下の通りです。
|
脱炭素化が必要な理由 |
サプライチェーン全体の排出量を削減する必要がある SBTはサプライチェーン全体での削減を求めている 日本政府もサプライチェーン全体での脱炭素化を推進している |
|
脱炭素化を進めるメリット |
ESG投資の対象になりやすくなる ビジネスチャンスが増加する 優秀な人材を確保しやすくなる |
本記事で紹介した脱炭素化を進めるサプライチェーン企業の事例を参考に、サプライチェーン全体での脱炭素化に取り組んでみましょう。
アトミテックでは、委託先リスク管理の手順をまとめた委託先リスク管理ガイドを公開しています。ぜひ自社の委託先管理の参考になさってください。