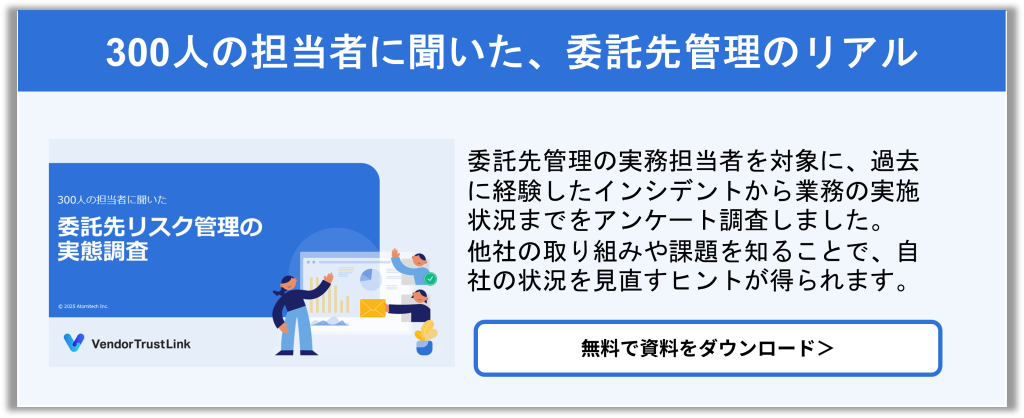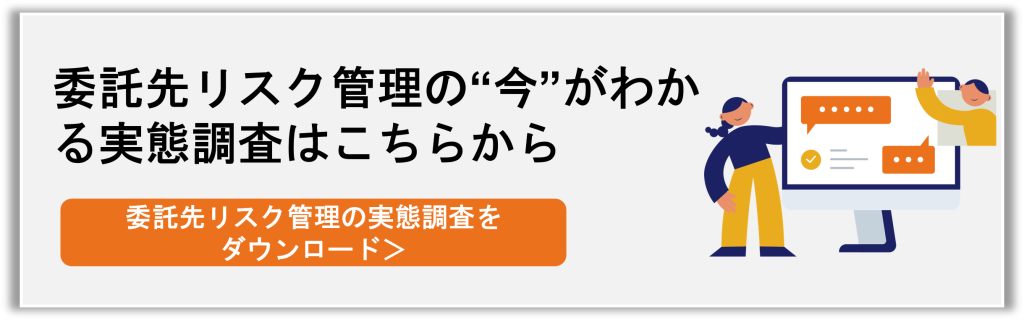「再委託とは何か」「再委託を許可するとどのようなメリット・デメリットがあるのか」「委託元が許可する際にはどのような点に注意すればよいのか」など、疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、再委託の概要から委託元が許可するメリット・デメリット、注意点、契約書の例文について解説します。
1. 再委託とは
再委託とは、委託先が委託元から依頼を受けた業務を第三者に再度委託することを指します。これは、業務の効率化や専門性の高い技術の活用を目的とすることが多いです。例えば、ソフトウェア開発のプロジェクトで、特定の技術に精通した企業に再委託することで、開発スピードや品質を向上させることができます。しかし、再委託を行う場合、情報漏洩や責任の所在が不明確になるリスクも伴います。そのため、契約書で再委託の条件を明確にし、管理体制を整えることが重要です。
■委託先・委託元とは
委託先とは、業務やサービスを代行してもらうために選ばれた企業や個人のことを指します。一方、委託元はその業務を外部に依頼する主体であり、通常は企業や団体が該当します。例えば、ある企業が製品の製造を外部の工場に任せた場合、その工場が委託先で、依頼した企業が委託元となります。再委託においては、この関係がさらに複雑化することがあります。委託元が許可を出すことで、委託先がさらに別の業者に業務を再委託する(再々委託)ことが可能となります。このような場合、委託元は再委託の許可を与える際に、信頼性や責任の所在を明確にする必要があります。
■再々委託とは
再々委託とは、元々の委託先がさらに別の業者に業務を委託することを指します。例えば、企業Aが企業Bに業務を委託し、企業Bがその業務の一部または全部を企業Cに再度委託する場合がこれに該当します。再々委託は業務の流れを複雑にし、管理が難しくなることがあるため、契約書での取り決めが重要です。再々委託は、委託元の許可が必要な場合が多く、契約書にその条件が明記されていることが一般的です。これにより、責任の所在を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。
■再委託と外注の違い
再委託と外注の違いは、主に契約関係と業務の流れにあります。再委託とは、委託した業務をさらに別の業者に委託することです。例えば、A社がB社に業務を委託し、B社がその業務をC社に再委託する場合です。一方、外注は特定の業務を外部の専門家や会社に依頼することを指します。再委託は、委託元の許可が必要で、契約書で明確に規定されることが一般的です。外注は通常、委託元の許可を必要とせず、直接契約を結びます。
■再委託を禁止することが多いケース
再委託を禁止することが多いケースは、委託元と委託先が委任契約・準委任契約を締結している場合です。
委任契約とは、法律行為の遂行もしくは遂行した結果を目的とした契約です。準委任契約とは、非法律行為の遂行もしくは遂行した結果を目的とした契約です。
民法644条において委任契約・準委任契約では、やむを得ない事態が発生した場合や委託先からの許可を受けていない場合には、再委任が禁止されています。
|
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
|
■再委託にあたらないケース
委託元と委託先が請負契約を締結している場合、委託先が第三者に業務を委託しても再委託にはあたりません。
なぜなら、請負契約は納期までに依頼内容を完成させることを目的とする契約だからです。
|
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
|
また、委託元と委託先が委任契約・準委任契約を締結している場合においては、委託先の派遣社員が業務を行ったとしても、派遣社員は第三者ではないため再委託にはあたりません。
【関連記事】
業務委託契約とは?雇用契約・請負契約との違いや委託する側のメリット・デメリットを解説
2. 委託元が再委託を許可するメリット
委託元が再委託を許可するメリットは以下の2つです。
|
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
■複数の委託先と契約する手間を削減できる
委託元が再委託を許可する1つ目のメリットは、複数の委託先と契約する手間を削減できることです。
委託元が再委託を許可しない場合、委託元が委託する業務に関して、それぞれの委託先と個別に業務委託契約を締結する必要があります。
一方、再委託を許可すれば、委託先が実際に業務を担当する事業者と個別に契約するため、委託元が委託先とだけ契約するだけで済みます。
契約書を作成したり報酬を支払ったりする手間を大幅に削減できるでしょう。
■生産性が向上する
委託元が再委託を許可する2つ目のメリットは、生産性が向上することです。
委託先1社で受注できる作業量には限りがあります。
製造業や建設業、IT関連業界では下請け・孫請けを前提とした企業が多く、再委託を禁止すると対応してもらえないケースもあるでしょう。
一方、再委託を許可すれば、作業を担当する人数が増え、専門の技術をもった人に依頼できることで生産性が向上します。
ただし、委託先が再委託したからと言って専門の技術を持つ人へ委託するとは限りません。
3. 委託元が再委託を許可するデメリット
委託元が再委託を許可するデメリットは以下の3つです。
|
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
■委託コストが増加する場合がある
委託元が再委託を許可する1つ目のデメリットは、委託コストが増加する場合があることです。
委託先が再委託を行う場合、委託先は再委託先へ報酬を支払う必要があります。
つまり、委託先では再委託先へ支払う報酬分の費用が発生するということです。
実際には再委託先へ支払う報酬分とは別に中間マージンも委託元が支払うことになるため、個別に依頼する場合より委託コストが増加します。
■品質が低下する場合がある
委託元が再委託を許可する2つ目のデメリットは、品質が低下する場合があることです。
委託元が委託先を選定する場合、依頼するかを自社の基準で判断できます。
一方、再委託では委託先が再委託先を選定するため、自社の基準を下回る恐れがあります。
再委託によって委託先で不足しているスキルを補える可能性はありますが、品質が保証されているわけではありません。
委託先が中間マージンを増やそうと考え、技術力が低い事業者へ再委託する可能性もあるわけです。
■情報漏えいが発生する可能性が高くなる
委託元が再委託を許可する3つ目のデメリットは、情報漏えいが発生する可能性が高くなることです。
再委託を禁止していても、委託先から情報が漏えいするリスクはあります。
しかし、再委託を許可した場合、委託元が委託先へ提供した情報は再委託先へも提供されることがあるため、情報に触れる人数が増加する分だけ、情報が漏えいするリスクも増加します。
【関連記事】
4. 委託元が再委託を許可する際の注意点
委託元が再委託を許可する際の注意点は以下の2つです。
|
それぞれの注意点について詳しく解説します。
■再委託先の監督義務について確認する
委託元が再委託を許可する際の1つ目の注意点は、再委託先の監督義務について確認することです。
委託元には委託先を監督する義務があり、委託先には再委託先を監督する義務があります。
つまり、委託先が再委託先を適切に監督しているかを委託元が監督する義務があるということです。
再委託先で情報漏えいが発生した場合、委託元が責任を問われたり、被害者から損害賠償請求されたりする恐れがあります。
また、情報漏えいの原因が再委託先だった場合でも、委託元が対応する必要があります。
|
また、委託先が再委託を行おうとする場合は、委託を行う場合と同様、委託元は、委託先が再委託する相手方、再委託する業務内容、再委託先の個人データの取扱方法等について、委託先から事前報告を受け又は承認を行うこと、及び委託先を通じて又は必要に応じて自らが、定期的に監査を実施すること等により、委託先が再委託先に対して本条の委託先の監督を適切に果たすこと、及び再委託先が法第23条に基づく安全管理措置を講ずることを十分に確認することが望ましい(※4)。再委託先が再々委託を行う場合以降も、再委託を行う場合と同様である。 |
■契約書で再委託を規定する
委託元が再委託を許可する際の2つ目の注意点は、契約書で再委託を規定することです。
委任契約・準委任契約では原則として再委託が禁止されているため、再委託を許可する場合には契約書に明記しておく必要があります。
また、どのような場合に再委託を許可するのか、再委託先に対する委託先の義務や責任範囲などについても明記しておきましょう。
【関連記事】
業務委託契約書とは?記載する項目や作成時の注意点、収入印紙の必要性について解説
5. 再委託に関する契約書の例文
■再委託を許可する場合
|
第〇条 第三者委託
|
■再委託を許可しない場合
|
第〇条 第三者委託
|
6. まとめ
今回は、再委託の概要から委託元が許可するメリット・デメリット、注意点、契約書の例文について解説しました。
委託元が再委託を許可するメリット・デメリット・注意点は以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
| 注意点 |
|
委託先と委任契約・準委任契約を締結する場合、再委託について契約書に明記しておくことが重要です。
また、安易に再委託を許可してしまうと、自社が責任を負うことになったり、委託先を管理する手間が増えたりする恐れがあります。
アトミテックでは、委託先リスク管理の担当者300名への調査結果をまとめた「委託先リスク管理の実態調査」を公開しています。ぜひ他社の取り組み状況や最新の傾向を知る参考になさってください。