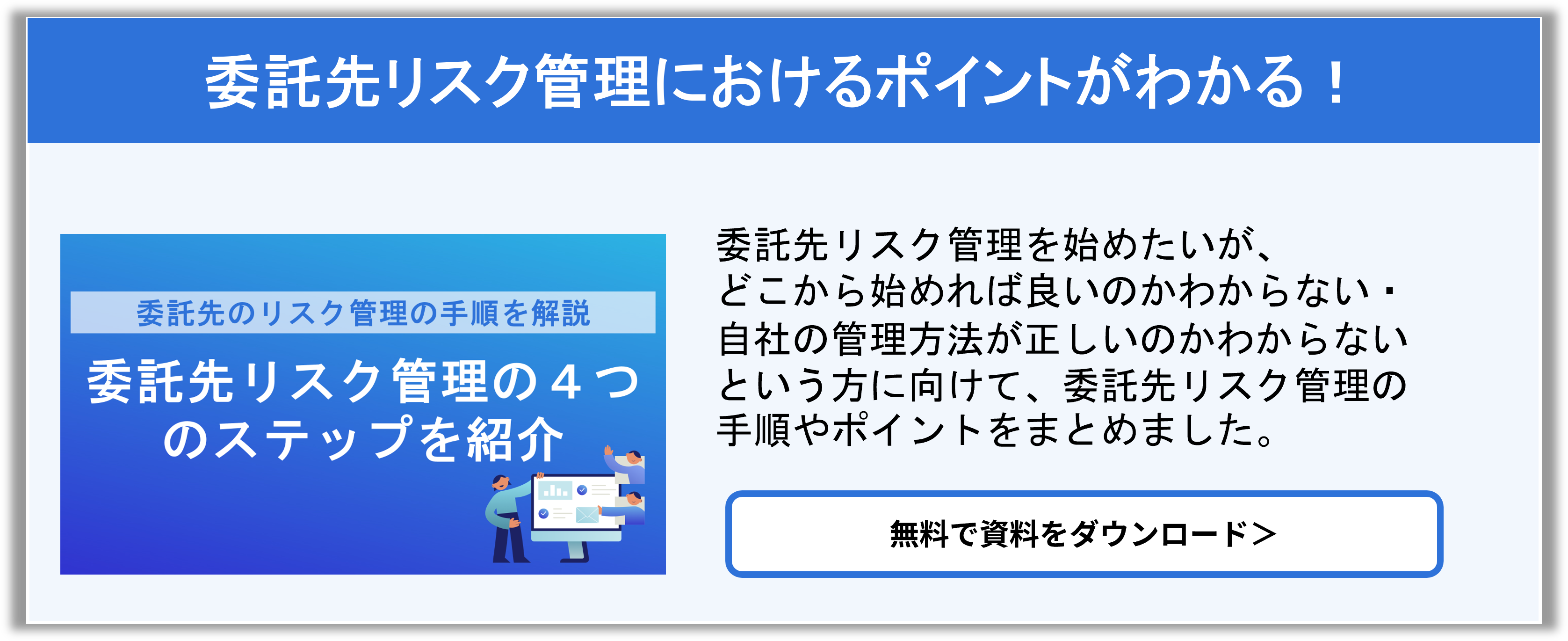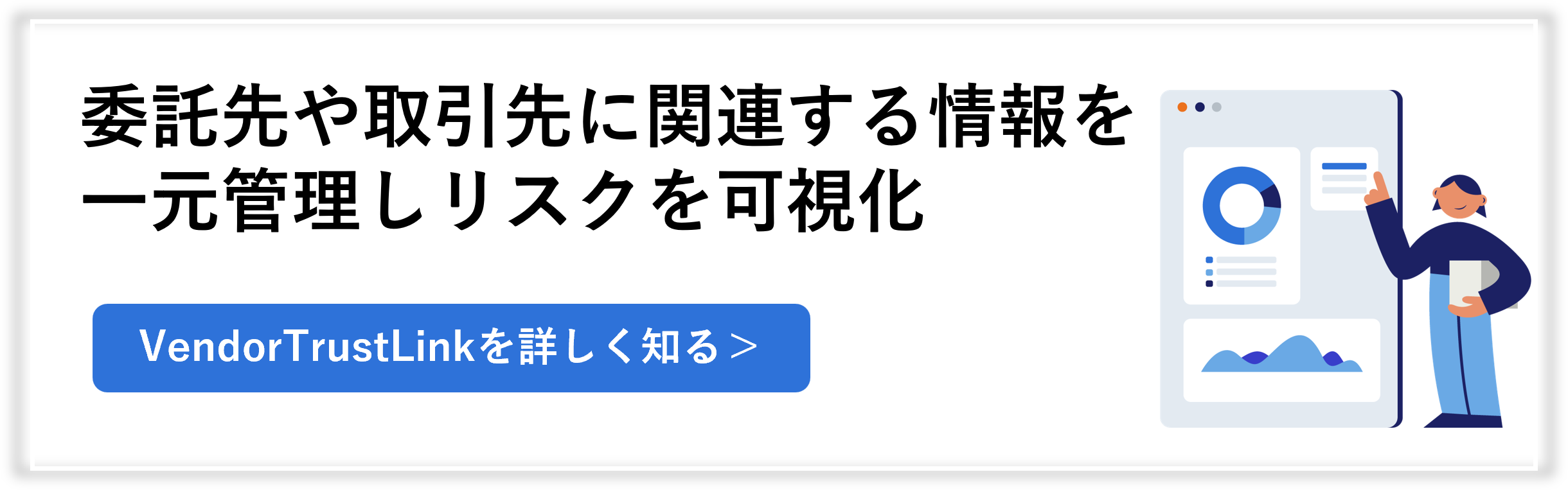「ITリスクマネジメントとは何か」「ITリスクマネジメントではどのようなリスクに対応するのか」「ITリスクマネジメントを実施するためにはどうすればよいのか」など、疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、ITリスクマネジメントの概要から重要な理由、主なITリスク、ITリスクマネジメントを実施する手法について解説します。
1. ITリスクマネジメントとは
ITリスクマネジメントとは、自社で発生するITリスクに対し、リスクマネジメントを実施することです。
分かりやすく言えば、ITリスクに特化したリスクマネジメントと言えるでしょう。
ITリスクとは、情報技術に関連する潜在的な問題や障害を指します。具体的な例として、システムの不具合、セキュリティ侵害、データの損失などが挙げられます。ITリスクは企業の業務に大きな影響を与える可能性があるため、適切な管理が不可欠です。そこで重要となるのが「ITリスクマネジメント」です。このプロセスを通じて、企業はリスクを特定し、評価し、適切な対応策を実施することが求められます。
まず、ITリスクマネジメントの第一歩はリスクの特定です。企業は自社のシステムやデータがどのような脅威にさらされているのかを把握する必要があります。例えば、日本国内の企業では、自然災害によるデータセンターへの影響や、サイバー攻撃の増加が懸念されています。次に、特定したリスクを評価し、どのリスクが最も影響が大きいかを判断します。これにより、優先的に対策を講じるべきリスクを明確にすることができます。
次に、実施する対応策についてです。リスクに対する具体的な対応策には、システムのバックアップ体制の強化や、セキュリティソフトウェアの導入、従業員へのセキュリティ教育の実施などがあります。特に日本では、個人情報保護法が厳格化されているため、データの取り扱いに関する対策も重要です。
また、ITリスクマネジメントは一度実施して終わりではありません。技術の進化とともにリスクの内容も変化し続けるため、常に最新の情報を元に対応策を見直し、改善を図ることが求められます。例えば、新たなサイバー攻撃手法が出現した場合、それに対抗するための新しいセキュリティ対策が必要となるでしょう。
このように、ITリスクマネジメントは企業の安全性を確保するために不可欠なプロセスです。特に日本国内の企業においては、国際的な競争力を維持するためにも、リスク管理の重要性が増しています。したがって、企業はリスクマネジメントを戦略的に進め、業務の安定性を確保することが求められます。
■リスクマネジメントとは
リスクマネジメントとは、企業が経営を行う際に遭遇する可能性のあるリスクやその影響を正確に理解し、事前に対策を講じることで危機を回避したり、損失を最小限に抑えたりするためのプロセスです。
企業の価値を維持または増大させることを目的として、リスクマネジメントを実施します。
リスクマネジメントを実施する手順は以下の通りです。
|
【関連記事】
2. ITリスクマネジメントが重要な理由
ITリスクマネジメントが重要な理由は以下の通りです。
- IT技術を前提としたビジネスを展開する企業が多い
- 被害が発生すると大きな影響を受ける
それぞれの理由について解説します。
■IT技術を前提としたビジネスを展開する企業が多い
ITリスクマネジメントが重要な理由の1つ目は、IT技術を前提としたビジネスを展開する企業が多いからです。
以前はTVCMや新聞といったオフライン広告を中心とした集客が主流でしたが、近年ではWEB広告を活用した集客の割合が増加しています。
また、勤怠管理や予算管理などについても、手書きやエクセルなどを使った作業から、WEBツール・システムを活用する企業が増加しています。
一見するとIT技術とは関係のないような業務においても何らかの形で関わっている事が多く、ITリスクが発生するとさまざまな業務へ影響を与える恐れがあります。
■被害が発生すると大きな影響を受ける
ITリスクマネジメントが重要な理由の2つ目は、被害が発生すると大きな影響を受けるからです。
社内のシステムやメール、ツール、サービスなど、多くの企業ではインターネット環境を前提としたIT技術が多数使用されており、IT技術は無視できないほどビジネスに大きな影響を与えています。
IT技術を活用することでスムーズにビジネスが展開できるようになった一方で、システムトラブルやサイバー攻撃、ヒューマンエラーなどでIT技術が使用できない状況に陥ってしまうと、業務が完全にストップしてしまう恐れがあります。
ITリスクマネジメントを実施することにより、上記のようなトラブルが発生することを事前に想定したうえで、予防対策や事後対応の準備をすることで、自社への被害を最小限に抑えることが可能です。
3. ITリスクの分類
ITリスクは主に3つの分類に分けることが可能です。
|
それぞれの分類について解説します。
■ハードウェアやソフトウェアの故障
ITリスクの分類の1つ目は、ハードウェアやソフトウェアの故障です。
具体的には、下記のようなトラブルが含まれます。
|
ハードウェアやソフトウェアの故障が発生すると、業務の停止やデータの損失が生じる可能性があります。企業では信頼性が重視されるため、システムの不具合は顧客からの信用を失うリスクを伴います。
このようなリスクを回避するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。ハードウェアの点検やソフトウェアのアップデートを定期的に行うことで、故障の予兆を早期に発見し、未然に防ぐことが可能です。また、バックアップの実施も重要です。データの損失を防ぐために、クラウドストレージや外部ハードディスクを活用したデータのバックアップは、ITリスクマネジメントの基本となります。
さらに、故障が発生した際には、迅速に原因を特定し、再発防止策を講じることが求められます。故障の原因を分析することで、同じ問題が再び発生するのを防ぐことができます。また、予備のハードウェアやソフトウェアを用意しておくことも、迅速な復旧を可能にします。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、業務への影響を軽減することができます。
■災害によるトラブル
ITリスクの分類の2つ目は、災害によるトラブルです。
地震や台風といった自然災害は、データセンターや通信インフラに大きな影響を与える可能性があります。システムダウンやデータの消失といった事態が発生し、企業の活動に重大な支障をきたすことも少なくありません。
日本は地震大国として知られており、どの地域においても地震のリスクが存在します。また、台風の影響で通信インフラが損傷を受けることもあります。このような自然災害のリスクに対処するためには、ITリスクマネジメントの一環として、バックアップ体制の整備が必要です。データの分散保管を行うことで、特定の施設が被害を受けた場合でもデータを守ることができます。
さらに、災害発生時の対応計画を策定することも重要です。これには、緊急時の連絡体制の確立や、システム復旧の手順を明確にすることが含まれます。こうした準備を行うことで、自然災害による影響を最小限に抑えることが可能です。
■人的・組織的なトラブル
ITリスクの分類の3つ目は、人的・組織的なトラブルです。
セキュリティ対策が充実したIT機器を使用していたとしても、IT機器を使用する人間の操作ミスによる被害を防ぐことはできません。
以下のようなヒューマンエラーが発生すると、大きな問題に発展する恐れがあります。
|
また、サイバー攻撃や内部の犯行によるシステム障害もこの分類に含まれます。サイバー攻撃を受けてしまうと、自社が抱える機密情報や個人情報などが漏えいしたり、ウィルスに感染したシステムや暗号化されたデータの復旧と引き換えに身代金を要求されたりする恐れがあります。
4. ITリスクマネジメントの手法
ITリスクマネジメントの手法は以下の4つです。
|
それぞれの手法について解説します。
■BCP(事業継続計画)を策定する
ITリスクマネジメントの手法の1つ目は、BCP(事業継続計画)を策定することです。
BCPとは、自然災害やパンデミック、テロ攻撃、サイバー攻撃、不正行為、システム障害などの不測の事態が発生した場合に被害を最小限に抑え、早期復旧して事業を継続できるようにするための計画を指します。
不測の事態が発生することを想定し、自社が直接受ける被害に対して備えることで、自社が受ける影響を軽減することが可能です。
【関連記事】
BCP(事業継続計画)とは?策定する目的やメリット、策定方法を解説
■システムを強化する
ITリスクマネジメントの手法の2つ目は、システムを強化することです。
サーバーの冗長化やデータのバックアップ、ネットワークの冗長化をしておくことで、故障などで停止したり利用できなくなった際にもシステムが稼働し続けられたり、データの損傷・消失を防ぐことができます。
特に重要なシステムにおいては上記の対策を取っておくと良いでしょう。
■リテラシー教育を実施する
ITリスクマネジメントの手法の3つ目は、ITリテラシー教育を実施することです。
ITリテラシーとは、IT機器・ITサービスの仕組みや構造の理解、使い方、使用時のマナー・モラルなどに関する能力を指します。
たとえば、日常的に利用する機会が多いメールについても、TO・CC・BCCの違いや使い方を理解できていなければ、間違った相手にメールを送信してしまい、機密事項が社外へ流出する恐れがあります。
また、自社SNSアカウントを運用する場合においても、不適切な投稿をすれば、炎上して自社の評判が大きく低下するかもしれません。
リテラシー教育を実施することで、ITリスクが発生する可能性を低下させることができ、発生した際にも早期対応が可能になります。
■取引先のリスク管理をチェックする
ITリスクマネジメントの手法の4つ目は、取引先のリスク管理をチェックすることです。
ITリスクは自社を起因とするものばかりではなく、取引先を起因としたITリスクも想定されます。
委託先・取引先がBCP(事業継続計画)を策定しているか、システムの冗長化等を行っているか、社員へのリテラシー教育を実施しているかなど、委託先・取引先のリスク管理対策を定期的にチェックすることが重要です。
【関連記事】
委託先管理とは?目的や必要な理由、実施する際のポイントを解説
5. まとめ
今回は、ITリスクマネジメントの概要から重要な理由、主なITリスク、ITリスクマネジメントを実施する手法について解説しました。
近年ではインターネット環境やIT技術を活用したビジネス環境が欠かせないものとなっており、企業がリスクマネジメントを実施する上でITリスクへの対応は重要な要素です。
また、取引先とネットワークを構築してビジネスを展開するケースも増加しているため、自社だけでなく取引先のリスク管理状況をチェックする必要があります。
■委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」
弊社では、委託先管理を効率化したい事業者に向けて、委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」を提供しています。
委託先や取引先のITリスクの対応状況確認も、VendorTrustLinkで自動化することができます。
委託先リスク管理業務において以下のような課題を抱える事業者におすすめのサービスとなっています。
- チェックシートの送信や回収が手間
- 委託先一覧の管理や更新ができていない
- 業務が属人化しており後継者がいない
委託先管理にお悩みであれば、製品についてお気軽にお問合せください。