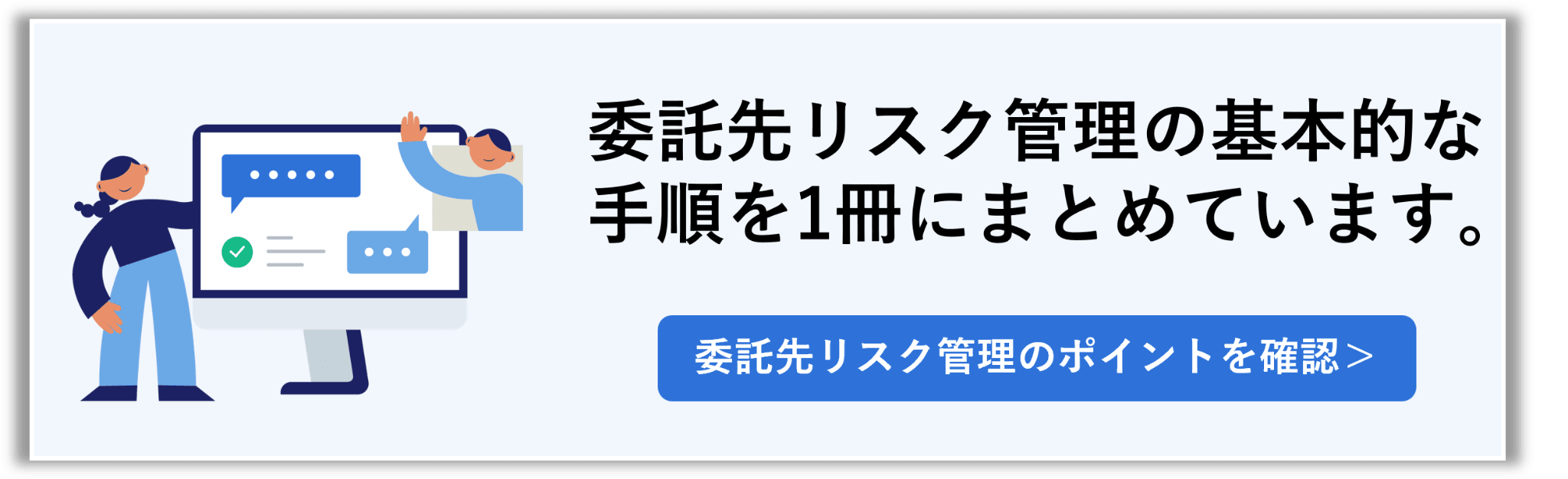「サプライチェーンリスクとは何か」「どのようなサプライチェーンリスクがあるのか」「どうやってサプライチェーンリスクの対策をすれば良いのか」など、疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、サプライチェーンリスクの概要から具体例、対策方法について解説します。
1. サプライチェーンリスクとは
サプライチェーンリスクとは、サプライチェーンを要因とした、自社に発生するリスクです。
取引先が倒産することで連鎖的に倒産してしまうリスク、自然災害によってサプライチェーンからの原材料・商品の供給が停止することで自社の事業が継続できなくなってしまうリスクなどの物理的なリスクがあります。
近年では、サプライチェーン攻撃を代表とする情報セキュリティリスクも増加しています。
取引先や委託先を起因として発生するため、従来のように自社だけでリスク対策を実施しても完全に防ぐことは困難です。
特に製造業のようにさまざまな企業との取引を前提とした事業を行う企業の場合、サプライチェーンリスクが発生すると自社の事業を一時的に停止することになったり、再開までに時間がかかってしまったりするかもしれません。
サプライチェーンリスクの被害を最小限にするには、サプライチェーンリスクを分析・評価・対策するサプライチェーンリスクマネジメントを実施することが重要です。
■サプライチェーンとは
サプライチェーンとは、自社商品の原材料の調達から製造、在庫管理、配送、販売までの一連の流れです。
上記の流れを担う企業を、サプライチェーンと表現するケースもあります。
サプライチェーン全体の効率を高めるためには、サプライチェーンに関わる企業同士が協力・連携するサプライチェーンマネジメント(SCM)を実施することが重要です。
【関連記事】
■サプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)とは
サプライチェーンリスクマネジメントとは、サプライチェーンリスクを分析・評価・対策することです。Supply Chain Risk Managementの頭文字を取って、SCRMと表記される場合もあります。
サプライチェーンリスクはサプライチェーンを起因として発生するリスクなので、自社で発生するリスクに対して対策を実施しても、リスクの発生を防止したり被害を抑えたりすることは困難です。
サプライチェーンリスクマネジメントを実施することで、サプライチェーンリスクの発生を防止したり、被害を抑えたりすることができます。
【関連記事】
サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?取り組むメリット・デメリットと企業事例を解説
■サプライチェーン全体での脱炭素化が求められている
日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現させることを目指しており、環境省が実施する「脱炭素経営による企業価値向上促進プログラム」では、以下のようなサプライチェーン全体での脱炭素の取り組みを推進しています。
- SBTやRE100(※1)などの目標設定の支援
- SBTやRE100などの目標に向けて削減行動の支援
- TCFD(※2)に沿った気候変動リスク・チャンスを織り込む経営の支援
サプライチェーン全体で脱炭素化を進めることが求められているのは、効率良く脱炭素化を進めるためには、個別の企業で排出量を削減するだけでなくサプライチェーン排出量を削減する必要があるからです。サプライチェーン排出量は、サプライチェーンに関わる個別の企業から発生する温室効果ガスの排出量だけでなく、サプライチェーンの一連の流れの中で発生する温室効果ガスも含めた排出量を指します。
【関連記事】
サプライチェーン全体での脱炭素化が必要な理由と進めるメリットを解説
■事業を継続できる状態へ迅速に修復する必要がある
サプライチェーンにおいては、事業に関わる企業がなんらかの危機によって役割を担えなくなると、サプライチェーンに関わるすべての企業が事業を継続できなくなる恐れがあります。元の状態に戻るまでに時間がかかり過ぎると、被害が拡大してしまうかもしれません。
サプライチェーン全体に与える被害を軽減し、事業を存続させるためには、それぞれの企業が事前にリスクを予測し、迅速に対応できる能力を持つことが重要です。
【関連記事】
サプライチェーンにおけるレジリエンスとは?求められる要因と高める方法を解説
2. サプライチェーンリスクが発生する要因
サプライチェーンリスクが発生する要因は以下の通りです。
|
■環境的要因
サプライチェーンリスクが発生する要因の1つ目は、台風や地震、津波といった自然災害や新型コロナウィルスに代表されるパンデミックなどの環境的要因です。
台風や大雪が発生すると一般道・高速道の通行規制や鉄道・航空機の運行停止により、予定した時間に資材が到着しなくなるなど、物流がストップする恐れがあります。
また、地震や津波が発生すると、主要な道路に被害が出て迂回する必要があるかもしれません。
2011年に発生した東日本大震災では地震と津波によって多くの企業で被害が発生し、サプライチェーンに大きな影響を与えました。
また、2024年1月1日に発生した能登半島地震では、幹線道路の大規模な土砂崩落・陥没・地割れが発生、トンネルや橋梁などの構造物も損傷し、最大42路線の87カ所(1月4日時点)が通行止めとなっています。
日本随一と言われる繊維産業のサプライチェーンが停止しただけでなく、自衛隊や近隣自治体による救命活動や物資輸送にも大きな影響を与えました。
■地政学的要因
サプライチェーンリスクが発生する要因の2つ目は、テロや政治的な不安といった地政学的要因です。
2023年11月以降、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が紅海を航行する船舶への攻撃を繰り返しており、11月19日には日本郵船が運行する貨物船が拿捕されました。
また2024年1月26日には紅海周辺のアデン湾で石油タンカーがフーシ派によるミサイル攻撃を受け火災が発生しました。
紅海を通るコンテナ船のおよそ90%は、スエズ運河ルートからの迂回を余儀なくされたようです。
貨物輸送業の業界団体の英国国際貨物協会(BIFA)は、運賃とサーチャージの上昇や航行スケジュールの混乱、欠便の発生、保険料の増加など、サプライチェーンへの影響について声明を発表しています。
【参考記事】
イエメン・フーシ派による紅海での船舶攻撃で、世界の物流が混乱
■経済的要因
サプライチェーンリスクが発生する要因の3つ目は、為替変動や原料の価格変動といった経済的要因です。
2022年2月24日にロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され、ウクライナ情勢が緊迫したことにより、小麦や半導体、原油など海外からの輸入割合が高い原材料の価格が高騰しました。
価格転嫁が困難な中小企業の経営を圧迫し、製造業を中心としたグローバルサプライチェーンの脆弱性が浮き彫りとなっています。
世界中のリソースを活用するグローバルサプライチェーンは、最適なコストと品質で製品を提供するための重要な手段です。特に、製造業や小売業においては、競争力を維持するために欠かせない要素となっています。生産拠点を世界中に分散することにより、労働力や原材料を確保するコストを大幅に削減できます。例えば、日本と比べて人件費が低い地域で生産を行うことで人件費を抑えることができ、日本国内での製造では実現が難しい低コストでの生産が可能になるわけです。
【関連記事】
グローバルサプライチェーンとは?メリット・デメリットや企業事例を解説
■サプライチェーン攻撃
サプライチェーンリスクが発生する要因の4つ目は、サプライチェーン攻撃です。
サプライチェーン攻撃とは、ターゲット企業に対して直接仕掛けられたサイバー攻撃ではなく、セキュリティ対策が不十分なサプライチェーンを経由して仕掛けられるサイバー攻撃を指します。
大手企業や上場企業など規模の大きい企業は強固なセキュリティ対策を実施しているケースが多いため、サイバー攻撃の被害を最小限に抑えることが可能です。
一方、中小企業や個人事業主など規模が小さい事業主は、サイバー攻撃を仕掛けるメリットが少ないことからセキュリティ対策がおろそかになっているケースがあります。
サプライチェーン攻撃は、セキュリティ対策が甘いサプライチェーンに対して先にサイバー攻撃を仕掛け、サプライチェーンとターゲット企業の繋がりを悪用してターゲット企業へサイバー攻撃を仕掛ける仕組みです。
サプライチェーンと関わりのある企業同士は頻繁にメールのやり取りを行ったりシステムを共有したりするなどネット上で繋がっているため、取引先や委託先がサイバー攻撃を受けてしまうと、自社もサイバー攻撃を受けてしまう恐れがあります。
【関連記事】
■コンプライアンス違反
サプライチェーンリスクが発生する要因の5つ目は、コンプライアンス違反です。
自社と取引のある企業が法令に違反すると、罰金などの処罰を科されたり、企業イメージが大きく低下したりする恐れがあります。
欧米圏の顧客や取引先がいる場合は特に強制労働や児童労働に対して厳しい目が向けられている他、虚偽表示等のコンプライアンス違反で摘発されているケースもあります。
人権問題に対する関心が強い欧米諸国では人権デューデリジェンスが義務化されており、海外へ進出する企業だけでなく日本国内でビジネスを展開する企業においても、人権を尊重する取り組みが重視されています。
人権デューデリジェンス(Due Diligence)とは、過酷な労働環境や賃金未払い、児童労働、強制労働などの人権侵害が自社の企業活動に与える影響を調査・分析し、リスクを抑える取り組みを指します。
【関連記事】
サプライチェーンで人権尊重が重視されている理由と人権侵害の影響を解説
3. サプライチェーンリスクの具体例
サプライチェーンリスクの具体例は以下の通りです。
|
■物流の停滞
サプライチェーンリスクの具体例の1つ目は、物流の停滞です。
製造業では販売する商品の原材料が確保できなければ生産がストップしますし、販売業ではメーカーや卸売りから商品が供給されなければ消費者へ商品を販売することができません。
サプライチェーンリスクの中でも物流の停滞は大きなリスクであり、問題が解消されるまでに時間がかかってしまうと、事業の存続にも大きく影響する恐れがあります。
■システム障害
サプライチェーンリスクの具体例の2つ目は、システム障害です。
サプライチェーンでは同じシステムを共有するケースがあるため、システム障害が発生するとサプライチェーン全体の流れにも大きな影響を及ぼすかもしれません。
システム障害が発生する要因としては、IT機器の不具合やネットワーク回線の不調だけでなく、サイバー攻撃によるウィルス感染やランサムウェア感染もあります。
■人員不足
サプライチェーンリスクの具体例の3つ目は、人員不足です。
自社の人員が十分に確保できていても、取引先側で人員が不足していると計画通りに事業を進めることができません。
近年では、新型コロナウィルスの蔓延による出勤停止や制限で、工場の稼働が低下したり、工場が閉鎖したりするケースがありました。
大雪や大雨で公共交通機関が利用できなくなることで社員が出社できず、対応が遅れてしまうこともあるでしょう。
■連鎖倒産
サプライチェーンリスクの具体例の4つ目は、連鎖倒産です。
連鎖倒産とは、自社と取引のある企業が倒産することで、連鎖的に自社も倒産することを指します。
サプライチェーンでは関連企業の倒産が大きな影響を与える可能性が高く、対応が遅れてしまうと事業を縮小することを余儀なくされたり、資金繰りが悪化して倒産してしまったりする恐れがあります。
4. サプライチェーンリスクを軽減できる対策
サプライチェーンリスクを軽減できる対策(サプライチェーンリスクマネジメント)は以下の通りです。
|
■BCP(事業継続計画)を策定する
サプライチェーンリスクを軽減できる対策の1つ目は、BCP(事業継続計画)を策定することです。
BCPとは、自然災害やパンデミック、テロ攻撃、サイバー攻撃、不正行為、システム障害などの不測の事態が発生した場合に被害を最小限に抑え、早期復旧して事業を継続できるようにするための計画を指します。
不測の事態が発生した際に自社が直接受ける被害に対して備えるだけでなく、サプライチェーン全体が受ける被害が自社に与える影響を想定した上で準備しておくことで、サプライチェーンリスクを軽減することが可能です。
【関連記事】
サプライチェーンにおけるBCP対策とは?重要な理由と事例を解説
■サプライチェーン最適化を実施する
サプライチェーン最適化とは、原材料の調達から製品が消費者に届くまでの、サプライチェーン全体のプロセスを最適化することです。グローバル化が進む現代で企業が競争力を維持するためには、需要予測の精度向上や在庫管理の効率化、サプライヤーとの関係強化といった施策を実施し、サプライチェーン全体のプロセスを最適化する必要があります。
【関連記事】
■複数の企業と取引する
サプライチェーンリスクを軽減できる対策の2つ目は、複数の企業と取引することです。
特定の取引先のみから原材料の供給を受けて商品を生産している企業の場合、なんらかの理由によって取引先からの原材料の供給が停止すると、自社の生産も停止することになってしまいます。
1社から原材料の供給を受けるのではなく複数の取引先から供給してもらうことで、サプライチェーンリスクを分散でき、被害を最小限に抑えることが可能です。
【関連記事】
■取引先・委託先のリスク管理をチェックする
サプライチェーンリスクを軽減できる対策の3つ目は、取引先・委託先のリスク管理をチェックすることです。
サプライチェーンリスクは自社と取引のある企業を起因として発生するリスクなので、取引先・委託先のリスク管理が十分に行われていれば、自社に与える影響を最小限に抑えることができます。
取引先・委託先がBCP(事業継続計画)を策定しているか、効果的なセキュリティ対策を実施しているか、コンプライアンスを遵守しているかといった内容をチェックすることが重要です。
【関連記事】
委託先管理とは?目的や必要な理由、実施する際のポイントを解説
5. まとめ
今回は、サプライチェーンリスクの概要から具体例、対策方法について解説しました。
サプライチェーンリスクは自社と取引のある企業を起因として発生するリスクなので、サプライチェーンリスクを軽減するためには取引先・委託先のリスク管理が欠かせません。
自社で取引先・委託先のリスク管理を行うには手間と時間がかかりますが、委託先リスク管理サービスを利用することで、自社の負担を大きく軽減できます。
■委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」
弊社では、委託先管理に課題を抱える事業者に向けて、委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」を提供しています。
委託先や取引先に関連する情報を一元管理し、リスクを可視化できるサービスです。
委託先のリスク管理作業を効率化でき、監査にかかる工数を削減できます。
委託先管理にお悩みであれば、製品についてお気軽にお問合せください。
また、委託先リスク管理として企業が行うべきことをまとめた「委託先リスク管理ガイド」を公開しております。
リスク管理の必要性は認識しつつも、実際に対策を打てていなかったり、これまでのやり方を踏襲してしまったりしている方は、ぜひご参照ください。
下記のリンクより無料で資料をダウンロードいただけます。